ヨガをする上でアーユルヴェーダがお勧めな理由
ヨガをする上で、なぜアーユルヴェーダが重要なのでしょうか?この記事では、アーユルヴェーダの基本からヨガとの関係性、体質(ドーシャ)に基づいたヨガの実践法、そして現代生活における活用法までを詳しく解説します。
目次
アーユルヴェーダとは
ヨガをしている人や、ヨガを学んでいる人であれば一度は耳にしたことがある「アーユルヴェーダ」という言葉。しかしアーユルヴェーダーが何なのか、なぜヨガとアーユルヴェーダが近い存在なのかということを理解している人はあまり多くはないのかもしれません。
日本ではアーユルヴェーダー🟰マッサージ、リラクゼーションのニュアンスで捉えられることが多いですが、それはアーユルヴェーダの中のわずか一部分だけでありアーユルヴェーダーとはヨガと同様に5000年以上前からあるインド発祥の伝統医学となります。アーユルヴェーダとは、「生命の科学」という意味を持ちます。病気を対象として見ていく西洋医学に対し、アーユルヴェーダは個々を見ていく医療になります。ある病気に対してはこの治療と決まっている西洋医学とは違いアーユルヴェーダではなぜその病気になったのかという理由や根源を探りながらライフスタイル全般を変えていく、治療していく形態になっています。
ですのでアーユルヴェーダでは病気になってしまってから、それを治すことより、病気になりにくい心身を作ること、病気を予防し、健康を維持するという「予防医学」の考え方の上に成り立っています。
アーユルヴェーダでは季節による1日の過ごし方、食べ物や食べ方、運動、人との関係など、生き方そのものを教えてくれる哲学でもあり、ヨガ、占星術なども含まれます。
例えば人が病気になったとき、ただ単に投薬や手術などの対症療法でその場を一時的に治療するのではなく、その人の「生き方」そのものを見つめ直すことで、病気のもとになる根源を断つという考え方になり、ここでいう「生き方」とは、食事・運動、睡眠などの生活習慣全般と、人間関係や考え方などの精神面も含まれます。
だからこそアーユルヴェーダでは何よりも『より良く生きる』ということを目的としています。
世界最古の医療システムであるアーユルヴェーダは、病気の治療や治癒だけでなく、私たちの生活全体にアプローチすることで健康な状態を保ち、長寿を図ろうとする考え方になります。
また、現代においてアーユルヴェーダは、世界保健機構(WHO)が伝統医療として重視し、その適切な活用を推奨するヘルスケアの一つであり、予防医学の観点からも大きな注目を集めています。
アーユルヴェーダとヨガの関係性とは
アーユルヴェーダが生き方そのものを良くしていく医療体系ということがわかった上で、ここからはなぜヨガとの関係性が強いのかについて解説していきます。
まずアーユルヴェーダの考えの根本になっている哲学にはインド哲学のサーンキヤ哲学がベースになっています。サーンキヤ哲学とはインド哲学の学派のひとつで、世界を精神原理と物質原理の2つで説明する二元論の考えを基準に考えています。このサーンキヤ哲学はヨガの論理的根拠ともされており、瞑想を理論的に深める学術でもあるのでヨガを学ぶ上でも根本原理がこのサーンキヤ哲学からきていることになります。だからこそヨガを学ぶ上でもアーユルヴェーダを学ぶ上でもサーンキヤ哲学の理解が必須になってくるので、ヨガやアーユルヴェーダの両者での考えが繋がることが大変多く出てきます。そしてアーユルヴェーダのライフスタイルの行いの中でもヨガをすることが運動習慣としても、精神の安定としても勧められています。このような事からアーユルヴェーダとヨガには考え方の原理が同じになっているため関係性も強くなっているのです。
ヨガをやる上でアーユルヴェーダーが役立つ理由
アーユルヴェーダは個々の体質を見ながらその人にあった健康になる為のライフスタイルや治療法を提案をしていくのですが、そこで個々の体質を見極めるための手段として「ドーシャ」という理論を使っていきます。このドーシャ理論とは私たちの体やその他のあらゆる物質は3つのドーシャが存在し、それは全ての人に宿っており、それぞれの働きで生命を支えているという考えです。3つのドーシャのバランスは人それぞれ違い、これは生まれた時に決まっており、それが個性でありその人の体質になると考えられています。3つのドーシャとはヴァータ、ピッタ、カファがありそれぞれのドーシャの割合は人それぞれ異なります。
また、年齢や季節、時間帯によってもドーシャバランスは変動します。春はカファが高まりやすく、秋はヴァータが乱れやすいなど、自然との調和もアーユルヴェーダでは重視されます。
この 『ドーシャ』という語源には、「異常」「病素」「増えやすいもの」「濁り」などの意味があるため、この意味の通り、ドーシャのバランスは常に同じではなく、日々変化するものです。
また、人それぞれ優勢なドーシャがあるが故に増えやすいドーシャがあり、その人本来持っているドーシャのバランスが増えすぎてしまったりアンバランスになったときに不調となります。
ですから自分のドーシャを知ることで、増えやすいドーシャを知り、増やしすぎないように調整することで、心身を健やかに維持、促進することが大切になってきます。
このドーシャ理論では体質ごとに合う食材、気候、運動など細かな分類があるのですが、そのため一般的に健康に良いと思われる食べ物や食材でも、ドーシャによっては逆に不調を招いてしまう事もあり得るのです。 また運動についても運動のやり方や運動量などもドーシャによって合う方法、合わない方法があるためここでヨガの練習方法にも繋がっていきます。そしてドーシャごとに適切なヨガの練習方法を知ることで、より健康を促進していけるヨガの実践を行えるようになるのです。
例えばヴァータ体質の人がは激しすぎる運動はヴァータを高めてしまい疲労を招くことでヴァータを乱してしまうのでヨガの練習ではハードすぎるものはあまり良くなかったり、逆にカファ体質の人は体質的に体が重くなりがちなので、運動量の多いハードなヨガをすることで心身のバランスが取れてきます。ですからどのドーシャを持っているのかによりヨガの練習方法を変えていくことでより健康になることができるのです。また、年齢によってもこのドーシャの優勢さは変化していくのですが特に老年期はヴァータが高まる時期なので激しすぎる運動はよりヴァータを高めてしまい健康に良いと思って行う運動や激しいヨガの練習が、自分自身を枯渇させてしまうことにも繋がってくるのです。
-
ヴァータ体質:過度な運動で疲れやすくなるため、リラックス中心のヨガが推奨されます。体を温め、安定感を生むポーズが効果的です。
-
ピッタ体質:情熱的で集中力が高い一方、怒りやすい傾向があるため、心身を冷ますような練習が有効です。
-
カファ体質:代謝が遅く、体が重くなりがちなため、ダイナミックな動きや筋力を使うヨガでエネルギーを活性化することが大切です。
アーユルヴェーダではドーシャは食べ物、季節、年齢、時間などから日々影響を受け変化をしていくので、それぞれの変化に自分の持つ本来のドーシャバランスが影響を受けやすいことを考慮した上でドーシャのバランスを保つためにも適切なヨガの練習を取り入れることが重要になっていきます。闇雲にヨガの練習をするのではなく自分にあったヨガの練習方法を取り入れるためにもアーユルヴェーダの知識があることでより最適なものになっていく為、ヨガをする人にはアーユルヴェーダの知識が大変役に立っていきます。
アーユルヴェーダとヨガのあるライフスタイル
アーユルヴェーダの考えを生活に取り入れながらヨガを練習していくことで、自分によりあった食生活、ライフスタイル、ヨガの練習方法を組み合わせていくことができるようになっていきます。
その為、ヨガだけを単体でやったり、アーユルヴェーダのみを取り入れるよりも両方を取り入れていくことで、自分にあった本当の意味での健康維持の方法が見つかります。
私たちの健康には身体と心の安定性が大切だからこそ食事、運動、ストレス緩和、生活習慣全てが繋がり相互に作用しています。アーユルヴェーダとヨガの知恵を組み合わせることでより相乗効果を増すことができるのです。
私自身もヨガとアーユルヴェーダを両方実践するようになってからより健康度が増したのを体感し、ヨガとアーユルヴェーダは姉妹科学と言われることの意味もより深く理解できてきました。
だからこそYOGAFORLIFEのRYT200、RYT300、RPYT85のヨガインストラクター養成講座ではこのアーユルヴェーダの知識を学ぶ時間を沢山入れています。ヨガとアーユルヴェーダを学びたい方には当校のスクールでの学びは大変お勧めです。
またアーユルヴェーダ基礎講座の学びも当校のオンライン講座で進めることができるのでこちらもお勧めです。
ヨガとアーユルヴェーダのある生活を一緒に始めてみませんか?
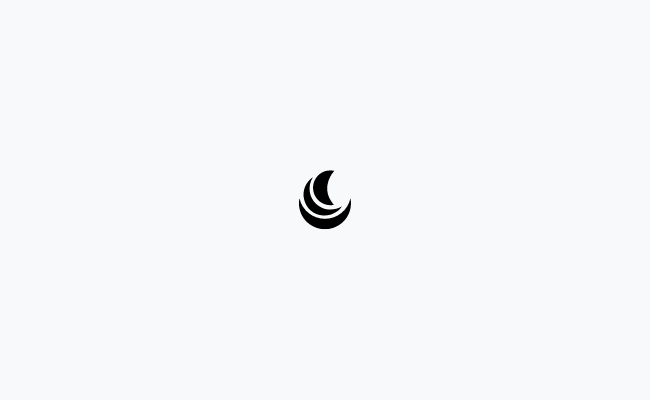


コメントを書く
このサイトはhCaptchaによって保護されており、hCaptchaプライバシーポリシーおよび利用規約が適用されます。